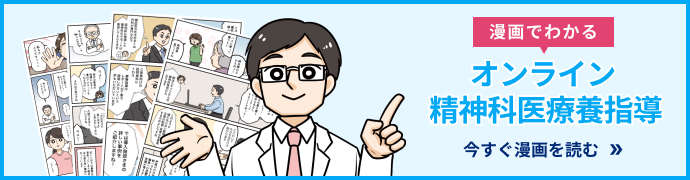2024年8月にドクターメイトがリリースした『オンライン精神科医療養指導』。今回は埼玉県桶川市の特別養護老人ホーム「クイーンズビラ桶川」の北村様に、導入から約11ヶ月後の効果や活用のエッセンスをお伺いました。
(取材協力:介護主任:樋口様、介護支援専門員:北村様)

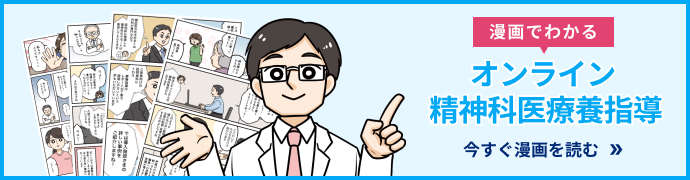
<導入の決め手>
現場負担の軽減と制度活用の両面から導入を決断
ー導入を決めた理由について教えて下さい
「私たちにとてもマッチしたサービスだ」それが、オンライン精神科医療養指導の第一印象でした。当施設の方針として、『どんな方でも受け入れる』という方針で入居者の受け入れをしていました。ただ、現場としては対応に苦労する部分もあり、現場を支える職員の負担軽減をしたいと考えました。「加算*」の仕組みも丁寧にご説明いただき、サービス費用もほぼほぼまかなえることを知り、迷うことなく契約に踏み切りました。
*オンライン療養指導による精神科定期的療養指導加算の算定を認める特養限定(詳細はこちら)
<導入前の課題>
閉鎖的な環境と対応の難しさが職員の心理的負担に
ー認知症ケアにおいては、どのような課題を抱えていましたか?
当施設では、認知症や精神疾患を抱える利用者様が全体の約3分の2を占めております。平均要介護度も4.1と比較的高く、重度の要介護者が中心です。そうした方々への対応において、職員がどのように接すればよいか分からないケースも多く、BPSDなどへの対応による心理的な負担が、日常的な悩みの一つとなっていました。
また、当施設は100床規模のユニット型で、1ユニットにつき利用者様10名を1名の職員が交代制で対応しています。ユニットという構造上、閉鎖的な空間となりやすく、ケアマネジャーや事務職が現場の様子を把握しづらく、フォローが入れづらいという課題もありました。
そのような環境のため、介護職員が一人で悩みを抱える場面も多く、利用者様に不穏症状が現れたとしても、すぐに周囲に助けを求めるのが難しい状況でした。
<療養指導浸透に向けて>
戸惑いの声もあったが、現場の理解は徐々に浸透
ー導入を伝えられた時、現場の反応はどうでしたか?
療養指導の導入にあたっては、現場に多少の不安がありました。紙での記録が主流だったため、Zoomなどのオンラインでのやり取りには抵抗感があったようです。看護師や介護職員からは、「何を質問すればよいのか」「どこまで質問してよいのか」といった戸惑いが見られました。
ですが導入後は「この前の療養指導では、こんなアドバイスがもらえたよ」「こんな方法もあるみたいだから、ちょっと試してみたら?」と、療養指導でいただいたアドバイスを共有することで、職員の中でも療養指導でのアドバイスが検討材料の1つとして受け入れられていきました。
<療養指導での相談内容>
ドクターメイトの活用で、本人と家族に寄り添うケアが実現
ー療養指導の体制や、現場との連携の進め方について教えてください
現在は私が主担当として、医師と1対1でやり取りを行っています。看護師や介護職員から日々の悩みを拾い上げ、それをもとに相談項目を組み立てるという体制です。相談員や主任、現場のスタッフにもヒアリングを行い、現場で実際に起きている課題を丁寧に整理しております。
医師からのアドバイスは、自分の中で咀嚼した上で現場に共有しており、カンファレンスの中で検討しながら、現場の実情に合った対応を皆で考えるようにしています。特に役立っていると感じるのが薬の適切な使用法についてです。
医師から副作用を含めた丁寧な説明があり、これまで使っていた薬をより効果的に使えるようになりました。たとえば抗精神病薬であれば、嚥下機能が低下するリスクや、それに伴う食事量の減少など、副作用を含めわかりやすくご説明いただけるため、適切な判断をする判断材料になっています。
かつては「精神科に連れていく」「病院に任せる」といった単線的な対応が多くを占めていましたが、薬のメリット・デメリットを知った上で、「どの選択がその方にとって最も納得できるか」という視点が持てるようになりました。
今では、医師の助言を一つの軸としつつ、専門的な知見と現場の経験、そしてご本人・ご家族の声をすり合わせながら、ケアのあり方を共に考えられる関係性が築かれつつあると感じています。

<導入後の効果>
精神科医との連携が定着し、安心感と前向きな受け入れ体制が生まれた
ー導入後、どのような変化がありましたか
導入後は、現場にいくつか変化が見られるようになりました。一つは、相談できる窓口ができたことで、職員の安心感が高まったことです。療養指導で医師に相談できる体制ができたことで、ご家族の方々にも、ケア方法について自信を持って説明できるようになったと感じます。スタッフ自身も「この対応にはちゃんと根拠がある」と納得感を持てるようになった印象を受けました。
職員の間でも「療養指導で相談してみよう」といった言葉が自然と出るようになり、これまで個人の経験に頼っていた認知症ケアが、専門的なアドバイスを前提に検討されるようになってきています。医師の意見を一つの判断材料として受け止め、それを踏まえて現場でどう対応するかを話し合う流れが定着しつつあるのではないでしょうか。
また、薬に対する理解も深まりました。たとえば睡眠薬については、「就寝30分前に服用するのが効果的」というレポートを医師からいただき、実際にその通りに運用してみました。それによって「寝つきが良くなった」という声が現場から上がるなど、効果を実感する場面も出てきています。こうした成功体験が職員の学びにつながり、知識の定着へとつながっていると感じます。

さらに現場の職員からも、「どんな利用者様でも受け入れられるのではないか」という前向きな気持ちも少しずつ育っています。以前は、徘徊などの行動がある方に不安を感じる職員が多かったのですが、「療養指導で相談できるから大丈夫」という安心感と、この1年間で蓄積されたノウハウや経験値が自信となり、「自分たちで対応できる」という姿勢に変わってきました。対応が難しい方についても「どうすれば快適に過ごしてもらえるか」を、自分たちで考える姿勢が身についてきたように感じます。
<今後の展望>
現場主導の体制構築に期待
ー療養指導を利用するに当たって、今後の展望があれば聞かせてください。
現在は私が仲介役として療養指導を運用していますが、最終的には 現場の職員自らが相談できる体制を目指しています。職員の中には「医師に相談するなんて緊張する」という方もいますが、実際はそんなことはありません。どんな相談にも丁寧に応えてくれるので、職員の方々にも活用してもらい、自主的に判断・実践できる環境を整えていきたいですね。
受け入れの幅を広げ、職員の成長を支える大きな一歩に

ー最後にオンライン精神科医療養指導の導入を検討されている施設様にコメントをいただきたいです
当施設のように「どんな方でも受け入れたい」という志を持つ施設にこそ、療養指導は有効に活用いただけると考えています。高齢者施設では、精神疾患を持つ方への対応に悩む場面も多く、同様の課題を抱える施設は少なくないのではないでしょうか。
「重度の認知症は難しい」「徘徊がある方は受け入れられない」といった理由で、入所を断らざるを得ないケースもあるかと思います。「オンライン精神科医療養指導」を導入することで、そのような方々への適切な対応が可能になり、受け入れのハードルを下げるきっかけとなるはずです。
また、特別養護老人ホームにおける療養指導の実施は、職員の成長を促し、仕事へのやりがいを高めるという点でも大きな意義があると感じています。現場で悩んでいる職員の方々には、「一人で抱え込まず、専門家に相談すること」の大切さをぜひ伝えたいです。相談できる窓口があることで、職場の雰囲気や職員の意識、そしてケアの質そのものが着実に変わっていくはずです。