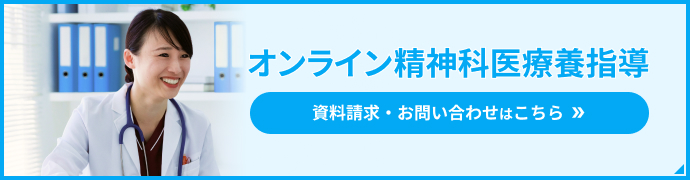今回は、精神科医の嘱託医の往診とオンラインの療養指導を駆使し、強固な認知症ケアを築いている、兵庫県豊岡市の特別養護老人ホーム「楽々むら」のみなさまにインタビューをしました。
(取材協力:介護副部長:田邊様、介護副部長:今井様)
- 楽々むら
- 楽々むらは、お年寄りを人生の先輩として敬い、それぞれの歩みを大切に、皆様がいきいきと和やかに安心して生活いただける毎日を目指します。


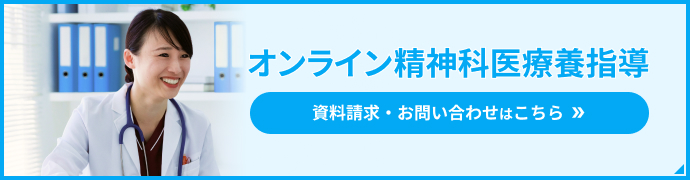
(Before/After)療養指導による効果
<導入前の課題>
月1回の往診に加え、日々の変化をタイムリーに相談できる場所が欲しかった
ー楽々むら様では認知症を専門としている精神科の嘱託医がいらっしゃいますが、そんな中で療養指導を導入した理由を教えて下さい
◆田邊様:当施設では、月1回精神科の先生が往診に来てくれています。2時間の時間をいただき、薬の処方を中心に、ケアについても相談させて頂いています。ただ次の往診を待たずに、もう少しタイムリーに相談できたら…という思いがありました。施設のご利用者様の多くは85歳以上で、1ヶ月の間に体調や周辺症状が大きく変化することも珍しくありません。そのため、嘱託医の先生の月1回の往診にプラス2回、細かいことを相談できるタイミングがあれば、非常にありがたいと思いました。
<導入の決め手>
ケアの選択肢が広がり、より多角的なアプローチが可能になることを期待
ー導入を決めた理由について教えて下さい
◆田邊様:療養指導は施設長からの提案でした。月2回の「療養指導」という形で、従来より高い頻度で頻繁に医師からアドバイスを受けられるようになり、嘱託医の先生の意見に加え、第三者の専門的視点を取り入れることで、ケアの選択肢が広がり、より多角的なアプローチが可能になるのではと提案を受けました。ご利用者さまのQOLを上げるために、精神科医との連携を通じて個別に最適化していくことを考えてくださってのことだと思います。
また、「加算*」を取得することで、コスト的な負担がないのも魅力でしたね。
*オンライン療養指導による精神科定期的療養指導加算の算定を認める特養限定(詳細はこちら)
<療養指導浸透に向けて>
抵抗があることを考慮し、段階的に一般職員の参加を促した
ー導入前に不安や懸念はありませんでしたか
◆田邊様:新しいシステムへの対応や、職員が情報入力に手間取らないかという懸念はありました。しかし、それは今回に限ったことではなく、新しいシステムを導入する際に、必ず起きる問題です。
そのため、導入してからも2~3ヶ月は私と今井が二人で療養指導で相談しながら、その内容を現場にフィードバックしていました。私たちが慣れてきたら、徐々にリーダーをはじめ一般職員の方にもサポートしながら利用してもらうようにしていきましたね。
一度参加した職員は、療養指導を受ける意義を体感
◆田邊様:精神科医の意見やアドバイスを現場が直接聞けるという現場への影響力は、私自身、もの凄いものを感じました。書面でアドバイス内容を見せても、なかなか療養指導の意義を感じることは難しいですが、一度参加するとその意義を感じてもらえます。
多職種連携という形で、医務、ケアマネ、相談員、一般職員と、段階的に参加をしてもらい、現在は半数近い職員が療養指導を受けています。療養指導は『チームを1つにする力』があります。客観的に第三者の目で見たアドバイスを受けられるようになったことは利益でしかないですね。
<療養指導での相談内容>
◆今井様:ケース検討という形でご利用者さまごとの相談をしています。内容としては落ち着かない、暴言、寝ずに歩き回る、よく転倒する、不潔行為など、よくある課題です。処方されている薬の相談だけでなく、薬を使わないケアについても相談しています。

薬物療法と非薬物療法を組み合わせ、 ケアの質が大幅に改善
ー嘱託医による往診の先生と療養指導をどのように組み合わせているのか教えてください
◆田邊様:環境調整や職員の接し方、処方調整など多角的なアドバイスをいただいています。その内容も嘱託医の先生に連携しながら、処方してもらうという流れでうまく棲み分けしてきました。
月2回、療養指導で相談できるようになったことで、少しずつ薬を抜いていけるようになった事例もあります。ご利用者の薬による状態の変化をデータを取りながら一緒に観察できることで、薬剤調整の提案をいただき、より細かな調整ができるようになりました。先生に相談していなければ、盲目的に同じやり方で進めてしまっていたこともあるので、やはり先生に相談して良かったなと思います。
ー外部の精神科医とのやりとりに、違和感ややりづらさはありませんでしたか?
◆今井様:当施設の療養指導の先生は都会的な印象で、正直最初は緊張しました。ですが今となってはそれが心地よく感じます。30分という短い時間でドライにサクッと返事をくれるので、とても気持ちがいいです。
療養指導の先生は、手法にこだわらず「困ったら薬を使ってもいいんだよ」「薬もいいけど、非薬物療法ならこういう手があるよ」とバランスのとれたアドバイスをくださるので、職員としても救われています。
<導入後の効果>
「相談できる安心感」が職員の自信になった
ー導入後、どのような変化がありましたか
◆今井様:最大の変化は、職員が安心感を得られたことです。以前は、ベテランの職員でも「これで合っているのか」と不安を抱えながらケアを行っていました。しかし、療養指導で精神科医からのアドバイスをもらえることで、自信を持って業務に取り組めています。
療養指導の場で医師から「その対応で大丈夫です」と褒められると、若い職員も「間違っていなかった」と確信を持てて嬉しかったという声が聞こえるようになり、大変励みになっています。
また、今までであれば、本当に困っている時に嘱託医の先生に相談していましたが、今は月2回の療養指導があるので、小さなことでも相談するようになりました。
処方を触らずにできるケアを、医療的な側面から助言してもらえる
◆今井様:薬に頼らない非薬物療法の選択肢が増えたのも大きな成果です。たとえば、自分の部屋が分からなくなり、迷ってしまうご利用者様がいました。この対策としてお名前を書いた矢印を、施設内の案内表示として設置したり、また迷い始めたら矢印の「色」を変えることで、徘徊されるご利用者様の動線が安定したという事例もあります。医師からの認知的観点での助言を現場で共有することで、職員一人ひとりの「ケアの引き出し」が増え、対応力が向上しました。
◆田邊様:また、そのようなアドバイスに対し、職員みんなが共有し合い、チーム一丸になって実行することで、チーム力が上がったと感じています。結果的に、組織の結束が強くなったのは導入以前には考えていなかった思わぬ成果でした。すぐに解決する問題ではありませんが、職員が一人で抱え込まず専門家と連携することで課題解決につながることを実感しています。

バイアスなく、第三者目線でのアドバイスがありがたい
ー外部だからこそ得られたことはありますか
◆田邊様:第三者で客観的であるからこそ、「気づかなかった」部分に手が届くアドバイスがありがたいです。自施設では、持ってる情報が多いからこそ、バイアスがかかってしまうこともあります。外部の先生だから気付けるものがあり、とても助かっています。
◆今井様:「施設と嘱託医」という関係性とは異なる、フラットな立場で意見交換ができるので、アドバイスいただいたことを自信を持って実行できますし、褒められた際も「自分は合ってたんだ、よかった」と思えますね。
ー現場の職員に変化はありましたか
◆田邊様:以前は施設長や私といった一部の管理職が抱えがちだった課題にも、現場職員が主体的に関わるようになり、「自分たちで解決する」という意識が芽生えています。何度も相談することで、職員も対応のレパートリーが増え、自発的に判断できる場面が増えてきたというのも大きいと思います。
自らのケアに自信を持ちつつ、「専門家の意見を取り入れることでさらに改善できる」という前向きな姿勢がみられるようになってきました。以前は医師に相談すること自体に緊張感を覚える職員もいましたが、現在は「療養指導で相談すれば的確なアドバイスが得られる」という安心感を持って臨めるようになっています。
介護職への採用効果も実感
ー採用面ではどのような変化がありましたか
◆今井様:介護福祉士養成施設(高校)の実習生からも当施設で働きたいという声が増えており、採用面でもプラスの効果が出ているという実感があります。ドクターメイトさんのサービス効果が就職の人気施設となっている一因になっているのは確かです。
<今後の展望>

組織全体で学び合い、地域から信頼される施設に
ー今後の楽々むら様としてのケア体制の展望についてお聞かせください
◆田邊様:様々な人の話を聞けるということは、とても有益だと思います。薬物療法であっても非薬物療法であっても、知っておけば対応の選択肢は増えますし、知っていて損はないと思います。ご利用者の人生がより良くなるために、今後も外部の知見を積極的に取り入れ、組織全体で学び合い、地域から信頼される施設として成長していきたいと考えています。
◆今井様:これまでも療養指導によって、非薬物療法に取り組んできましたが、今後はより一層力を入れていきたいと思います。その理由は非薬物療法であればアドバイスを頂いてすぐに実行でき、効果も実証されているからです。他の施設さんにも、ぜひお薦めしたいですし、困った時にすぐに相談できる環境があることは、施設や職員にとって非常に大きなメリットだと思います。