
光の苑は、認知症ケアに関する専門知識をもつことを目指して努力しています。認知症ケアで大切とされていること。それは「幸せの形、生活のスタイルは一人ひとりみな違う」という考えです。私たちは、一人ひとりを尊ぶことが利用者様の幸せな生活を支えるスタートだと考えています。
- 光の苑
- 今回は、長崎県壱岐市にある特別養護老人ホーム「光の苑」の遠藤様に、ドクターメイト導入の背景や、導入後の職員教育における効果、そして離島という地域特性を踏まえた活用の工夫についてお話を伺いました。制限のある医療資源の中で、いかに職員の判断力を高め、より良い認知症ケアを提供していくか――同じような環境で悩む施設の皆さまにとって、参考となるヒントが詰まっています。(取材協力:施設長 遠藤様)


《課題・効果》
課題
- 薬や症状に対する知識に自信が持てない中、判断を下すことが看護の重圧だった
- 離島で高度な医療を受けるためには、大きな負担が必要となる
効果
- 精神科医からの助言により、薬剤の正しい使い方や効果への理解が深まった
- 「今のケアや考え方で良かった」という確信が得られ、看護師の自信向上につながった
- 看護師が最新の知見や知識に基づく自律的な判断ができるようになった
- 薬物療法と非薬物療法のバランスが取れた対応が進みつつある
<導入前の課題>
認知症のケアや治療について幅広い知識を身につけるために導入を決断
ー導入前の課題についてお教えください
ここ壱岐では、精神科の病床がなく、必要があれば島外へ移送することになります。そうした中で、当施設は認知症の利用者様が多く、外来受診の際に症状を医師に報告し、内服指示を受けるといった、BPSD(行動・心理症状)への薬物療法に関する判断に苦慮する場面も多々ありました。
ー導入を決めたポイントは何だったのでしょうか?
ドクターメイトを導入すれば、BPSDに対する薬の処方や使用方法について精神科医から直接アドバイスをもらえるという点に、看護師たちが関心を示したことが大きなポイントでした。日常的に判断を迫られる場面が多いなかで、専門的な見解を聞けることは非常に心強かったようです。
加えて、「精神科医定期的療養指導加算」が活用できることも大きな後押しになりました。そこで私たちは、まず施設内の「教育の一環」として、小さな範囲から試験的にスタートすることにしました。
<浸透に向けて>
「少人数から広げる活用の輪」
ー導入はどのように進められたのでしょうか?
療養指導を「職員の学びの一環」という位置づけになればと思い、まずは私と主任看護師の2名で、療養指導を受けるところから始めました。
医師が入ると聞くと、どうしても「それに従わなくてはならない」と思いがちになってしまいますから、療養指導は医療判断に直接関与するものではない、ということを小さな範囲で様子を見ながら進めていく方針にしたのです。現在は、介護主任にも活用の幅を広げ始めており、今後は看護・介護の主任クラスを中心に、より多くの職員が利用できるよう体制を整えていく予定です。
<導入後の効果>
薬剤の正しい使い方や効果への理解が深まり、看護師の自信向上につながった
ー導入後、どのような効果を感じていますか?
ドクターメイトの精神科医とのやり取りを重ねる中で、看護職員の薬剤に関する知識が深まり、自信を持って対応できる場面が増えてきました。実際に療養指導を受けた人数は限られますが、それでも看護職の間では「薬剤の使い方について知識が深まり、対応に自信が持てるようになった」という声が出てきています。

これまでは、薬物療法などの新しい認知症ケアの手法は、その進め方や評価の仕方の知見や知識が不十分でどうしても「それまで成功していたやり方」を選択しがちでした。ですが療養指導で、外部の精神科医とディスカッションすることで、認知症ケアの選択肢や引き出しが増え、入居者様一人ひとりにとって『最適な認知症ケア』に向けた相談やアクションができるようになりました。
また「自分の考えや対応は、大きく間違ってはいなかった」「これで良かった」と確認できることも多くあり、看護師の安心感と自信につながっているようです。
理想的なケアに向けた実現方法の壁打ちができるように
新しいケア手法を教えていただくこともあれば、こちらが考えた新しいケア手法をブラッシュアップする「壁打ち」相手としても大変助かっています。
また、かかりつけの精神科医の先生への説明をより適切に行えるようになりました。これまでは、利用者の状況を十分に伝えられないという課題感がありました。ですが療養指導では、医師の判断軸や観察ポイントなども教えてもらえるので、適切な伝え方ができるようになりました。療養指導を通して、認知症の薬物療法への知識・理解が深まり、看護師とかかりつけの精神科医の先生との情報共有もより良いものとなっています。
また、精神科病床のある病院が無い離島である当施設では、「島外の病院に入院・搬送する」のは非常に大きな決定となります。その判断軸に大きな裏付けや自信を与える意味でも療養指導で得られる知見やディスカッションは役立っています。
薬物療法と非薬物療法のバランスが取れた対応が進みつつある
また、もともと非薬物療法を基本としていた当施設では、薬を使うことへの抵抗感もありました。療養指導で認知症の薬物療法について学ぶことで、徐々に効果を実感できてきたこともあり、「投薬もケアの一環である」という意識に少しずつ変わりつつあります。
<今後の展望>
その人らしい生活を送るための、医療的視点でのアプローチを介護でも
ー今後の活用について、どのような展望や課題がありますか?
現在ドクターメイトを実際に活用しているのは、主に私と看護主任、加えて数名の主任に限られています。今後は主任クラスを中心に、相談内容や効果を少しずつ共有しながら利用の輪を広げていきたいと考えています。

自分たちのケアや治療を、精神科の先生と一緒に検証できるのが療養指導
ー最後に、導入を検討している施設へメッセージをお願いします
いきなり「治療のための相談」と捉えるのではなく、「日々のケアを確認し、振り返るためのサポート」として導入すると、関係者の理解も得やすく、非常に取り組みやすいのではないかと思います。実際、私たちも「まずは学びのために使ってみよう」というスタンスから始めました。それが結果的に、職員の知識と自信を育てるきっかけになっています。
また、精神科の外来では聞けない話も、療養指導なら精神科医の先生に直接相談できます。精神科について学べる場はほとんどありません。ケアをする中で抱いた「これでいいのかな?」「他に方法はないのかな?」という疑問に対し、よりよくなるための方法を誰かと一緒に考えられるのは、とても心強いです。
特に、医療資源に制限のある離島のような地域では、職員の教育や相談体制の整備こそが、安心・安全なケアにつながっていくのだと実感しています。まずは少人数からでも始めて、職員の「学びの場」として活用してみることをおすすめします。
↓ オンライン精神科医療養指導の資料請求はこちら ↓
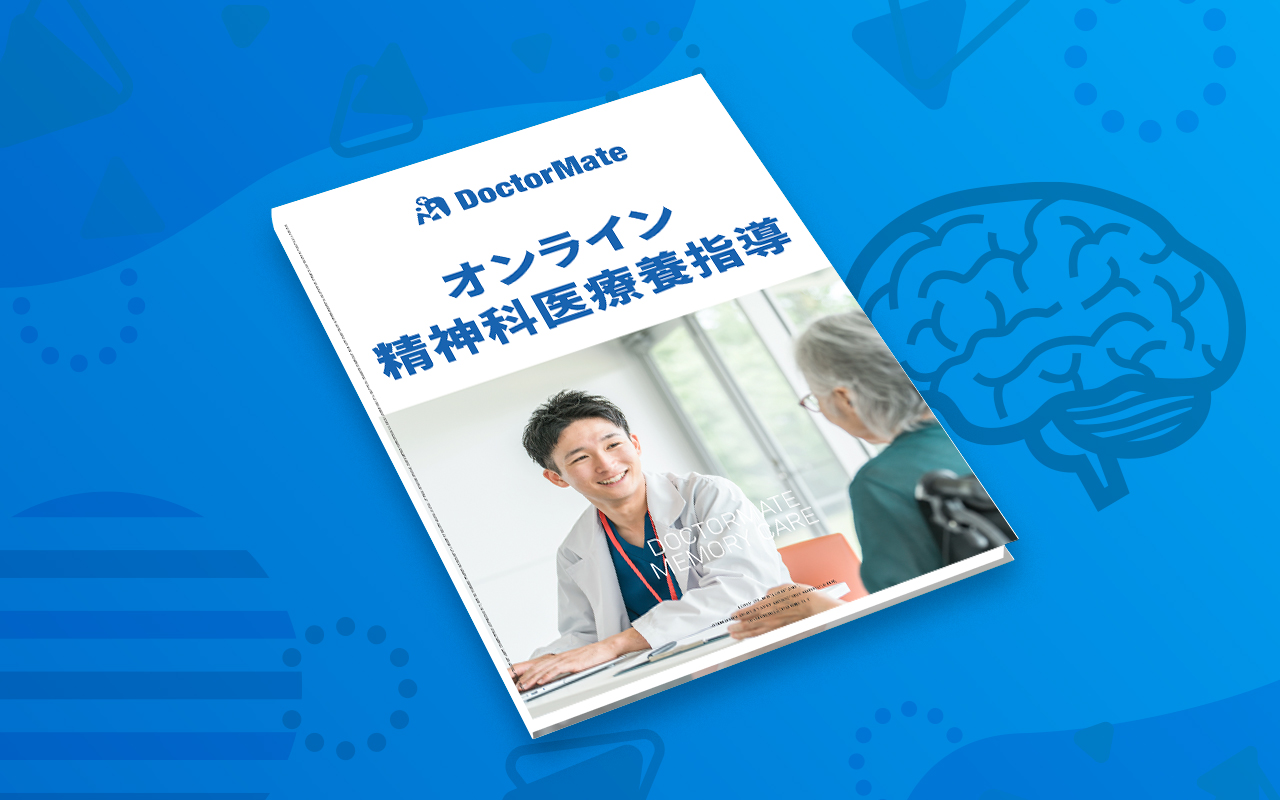
詳しい資料が無料でダウンロードできます。サービスの特徴・成功事例・活用方法・導入メリットなどをご覧いただけます。





