
急速に少子高齢化が進行する中で、国民皆保険制度をどのように維持していくかが現在の社会保障制度改革の主眼となっています。昨今の議論の主な方向性は負担と給付のバランス、より平たく言うと、社会保険料負担や窓口負担の公平性、診療報酬・介護報酬の適正な設定と給付内容の厳格化が中心です。
このうち前者に関しては、2年前の2022年10月に大きな制度変更が行われました。75歳以上が加入する後期高齢者医療制度での加入者の自己負担割合が以前は1割か3割のいずれかでしたが、新たに2割負担という区分が設けられたことです。ただ、この急激な変更により加入者の負担が急に増すことを避けるため、これまで軽減措置が講じられてきました。この措置がこの9月末で廃止されます。軽減措置廃止によりどのような影響があるかを解説します。
【アーカイブ配信】7月末に迫る「国民健康保険証の有効期限切れ」問題。高齢者施設がとるべき対応は? を見る
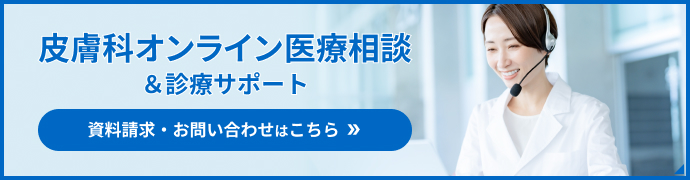
75歳以上の人すべてと65~74歳の人で一定の障がいの状態にある人が対象となる後期高齢者医療制度
直接的な影響を考える前に少し長くなりますが後期高齢者医療制度の成り立ちについて解説します。「後期高齢者医療制度とは何で、なぜこの制度があるのか?」がイマイチわかりにくいからです。
現在の日本の公的医療保険制度は、大きく「被用者保険」(職域保険)、「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」の3つに分けられます。被用者保険とは主に会社員などの現役世代向けの医療保険で、その中はさらに会社員とその扶養家族が加入する健康保険、船員とその扶養家族が加入する船員保険、公務員とその扶養家族が加入する共済保険の3種類があります。国民健康保険は、被用者保険の対象とならない自営業者や年金生活者など、日本国内に住所を有する75歳未満で他の医療保険制度に加入していない人を対象にした医療保険です。
そして今回の「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の人すべてと65~74歳の人で一定の障がいの状態にある人が対象となる医療保険で、2008年に創設された歴史が浅い制度です。
これ以前は1983年にスタートした70歳以上が対象の老人保健制度でした。同制度は市町村が運営主体で約3割が公費(国・都道府県・市町村)、約7割が国民健康保険も含む各保険者からの拠出金で運営され、対象となる高齢者は現役時代から加入していた各医療に加入を続けながら、定額あるいは定率の負担で医療を受けられるというものでした。
ちなみに老人保健制度時代の対象高齢者の自己負担額は2000年までは外来1回、入院1日当たりで定められ、外来では月当たりの回数、入院では月当たりの自己負担額にそれぞれ上限がありましたが、定額負担額も地域によって異なりました。
2001年からは医療費の高騰や自己負担の公平性担保の観点から外来、入院ともに定率1割負担となりましたが、この時も外来では月当たりの回数、入院では月当たりの自己負担額に上限設定が維持されました。
しかし、この制度の“欠点”は、財源の多くを保険者からの拠出金によって賄っていた点です。拠出金の算定は、当初は各保険者で使われた老人医療費で按分する「医療費按分」と、どの保険者も同じ老人加入率と見なして拠出金を調整する「加入者按分」を組み合わせて算出されていました。ところが1990年からは加入者按分のみで決定され、各保険者の加入高齢者割合の違いは考慮されず、結局は加入者の平均年齢が低い保険者ほど拠出金の負担が重くなり、不公平感が募ることになります。実際、1999年には健康保険組合連合会に加入する健保組合の97%が拠出金の支払いを一時差し止めた事件も起こりました。
また、この制度では保険料の納付先が各保険者に対し、拠出金を使うのが運営主体の市町村で、いわば財布の入口と出口が違うために使途がわかりにくいとの指摘もありました。これらを是正するために創設されたのが後期高齢者医療制度です。
新たに創設された後期高齢者医療制度の財源は、公費約5割、加入高齢者の保険料を約1割とし、残り約4割を各保険者からの支援金で賄う形となりました。保険者の支援金が老人保健制度時代の拠出金と異なるのは、拠出金は加入者数が基準になっていましたが、支援金は加入者数(人頭割)と加入者の給与などの所得水準による負担(総報酬割)を組み合わせて算出し、このうちの総報酬割の比率を多くすることで、所得水準が高い加入者が多く財政的に豊かな保険者の負担割合を増やしたことです。2017年からは総報酬割のみで各保険者の支援金額が決まっています。
また、老人保健制度時代の運営主体は市町村でしたが、後期高齢者医療制度では都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が行っています。より広域な運営主体にすることで市町村運営より財政的に安定することを念頭に置いたからです。
そして加入高齢者の自己負担は原則1割としつつ、例外として現役並み所得がある人は3割としました。現役並みの所得とは、同一世帯内にいる制度加入者の住民税課税所得145万円以上で、かつ世帯(加入者以外の現役世代の世帯員も含む)合計収入が 520万円以上(単身は383万円以上)の場合とされました。
2014年度からは3割負担基準が世帯内に課税所得145万円以上の加入者がいる場合のみに変更されました。ただし、この場合でも世帯収入が520万円未満(単身383万円未満)の場合は、申請により1割に変更できました。

2022年から新設された「2割負担」区分と配慮措置
そして冒頭で触れたように2022年10月から新たに2割負担という区分が設けられました。この背景には、現在の日本の人口構成の中で突出して人口が多い第二次世界大戦後の第一次ベビーブーム世代(1947~1949年生まれ:通称・団塊世代)が2022年には全員後期高齢者入りし、現在の制度設計のままでは現役世代が負担する支援金が増加し、負担の世代間不公平が拡大すると予想されたためです。
新たに導入された2割に該当するのは、▽同一世帯の制度加入者の中に課税所得が28万円以上の人がいる▽同一世帯の加入者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上、の2つを満たす場合とされました。厚労省の推計によると、新たに2割負担に該当する後期高齢者は約370万人とされています。
ただ、冒頭で述べたように2割負担となる人へは負担の急増緩和する配慮措置が取られました。具体的には外来受診での負担増加額の上限を1か月当たり3,000円とするものです。念のため言っておくと、月の外来受診の負担額上限が3,000円ではなく、2割負担となって新たに増えた負担額の月当たりの上限が3,000円です。なお、入院医療費では配慮措置はありませんでした。
ちなみに、同一月内に同じ医療機関に外来受診した場合は、1か月の負担増加額が3,000円となった時点以降は1割負担分のみを支払うことになります。また、後期高齢者医療制度の加入者で2割負担までの対象者は、高額療養費制度の外来での月当たり上限額が1万8,000円であるため、外来ではそれ以上の支払いは発生しません。
一方、複数の医療機関を受診して1か月の負担増加額が3,000円を超えた場合は、差額が後日高額療養費として払い戻されるという仕組みでした。
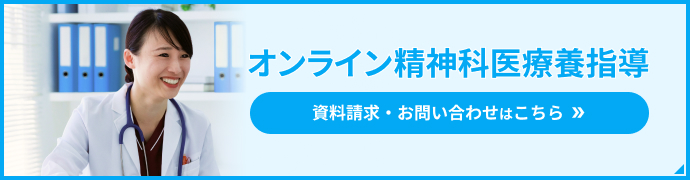
<医療費シミュレーション>配慮措置廃止後はどうなる?
さて2割負担の場合の実際の医療費はどのようなものでしょうか?ここで具体例として、高血圧症で月1回定期受診し、治療薬としてカルシウム拮抗薬のアムロジピンを処方されている事例で考えてみます。
一般にこの場合、診療報酬は以下のような計算になります。
医療機関 合計 803点
再診料 75点、生活習慣病管理料(I) 660点、処方料(院外) 68点
保険薬局 合計 174点
調剤基本料 45点、調剤管理料 60点、薬剤調整料 24点、服薬管理指導料 45点
これらはあくまで最低限の診療報酬でこれ以外に医療機関や薬局の施設条件や活動状況、患者の状態によってさまざまな加算がつくことがほとんどです。診療報酬は1点につき10円と計算されるのでこの場合、医療機関と保険薬局の合計医療費はこれら点数の合計977点に10円をかけた9770円となります。これとは別にアムロジピンの薬剤費がかかります。これも投与量や製造する製薬企業によって異なりますが、一般的な1日1回5mgの処方(ジェネリック医薬品)で考えると1ヵ月分は315円。
これらを合計すると、1ヵ月の医療費は1万85円で、1割負担で1,009円、2割負担ならば2,018円です。月当たり1,000円強の負担増です。高齢者の場合は複数の病気を有していることは珍しくありませんので、これ以上負担が増えることももちろんあり得ます。ただ、生活習慣病の場合に限って言えば負担増は限定的とも言えます。とはいえ、貯金が少なく、年金以外の収入がない場合は決して軽い負担増ではありません。
また、慢性疾患でも処方されている医薬品にジェネリック医薬品がないなどの場合は比較的負担は重くなります。
それ以上に高齢者の場合は体調の急変が起こりやすいため、そうした急性疾患による外来診療や入院の場合はかなり負担が重くなることが想定されます。ここで一例を挙げると新型コロナウイルス感染症の場合が該当します。
新型コロナウイルス感染症の疑いで受診し、陽性と判定され、モルヌピラビル(商品名:ラゲブリオ)を処方された場合の医療費を、診療報酬と調剤報酬の内訳とともに示します。
医療機関 合計 812点
初診料 291点、外来感染対策向上加算 6点、感染症対策実施加算 3点、SARS-CoV-2抗原検査(定性) 300点、免疫学的検査判断料 144点、処方箋料 68点
保険薬局 合計 123点
調剤基本料 45点、調剤管理料 4点、薬剤調整料 24点、服薬管理指導料 45点、特定薬剤管理指導加算 5点
医療機関と保険薬局の合計医療費は合計点数935点に10円をかけた9350円。ここまでは単一の生活習慣病よりちょっと高めぐらいです。
しかし、新型コロナは抗ウイルス薬が高額なことで知られています。モルヌピラビルは最近発売された400mgの錠剤が1錠4329.8円。通常1日4錠の5日間服用であるため、薬剤費は8万6,596円にもなります。
前述の医療費と薬剤費の合計は9万5,946円。この場合、1割負担ならば9,595円ですが、2割負担ならば1万9,190円です。ただし、後期高齢者で1割あるいは2割負担に該当する人は、高額療養費制度の月当たり外来医療費上限は1万8,000円となっているので、1,190円分は支払わなくてよくなります。とはいえ、2万円弱の窓口負担はなかなかハードな金額です。もしそのまま入院となればさらに負担は増えます。今回の2割負担の対象者の場合、高額療養費制度を使っても5万円超の支払いが必要になります。
いずれにせよ後期高齢者自身あるいはその家族、さらには介護関係者もとくに急性期疾患には要注意ということになります。



