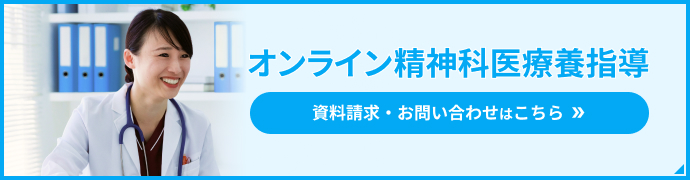暴言、暴力、徘徊、幻聴、独語、介護拒否・・・
認知症ケアの現場では、毎日の対応に追われて、「何が正しいのか」「どこを目指しているのか」が見えなくなってしまうこともありますよね。
なんとかしたい気持ちはあるけれど「どうしたらいいかわからない」。看護師も介護職員も、頼り先も相談先もないとなると、職員の心理的負担は増すばかりです。
そんな行き詰まりを打開するヒントが、“療養指導”という制度にありました。
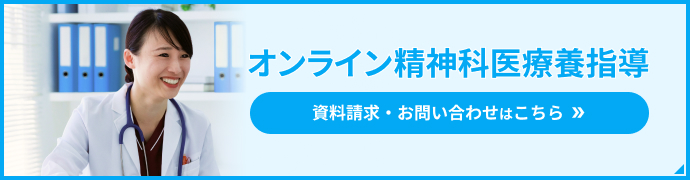
療養指導って何?どんなことをするの?
医師やその他の医療スタッフが、患者がより健康的な生活を送れるよう、食事、運動、服薬などの生活習慣に関する指導を行うことです。特養・地域密着型特養では、平成27年度介護報酬改定にて「精神科医療養指導加算*」が設定され、この制度を利用して精神科医が施設職員と一緒にご利用者のケアについて考える施設が増えています。
*認知症である入所者が1/3以上を占めている施設において、精神科医師による定期的な療養指導を月2回以上実施が必要
療養指導でできること
認知症の方のケアでは、「どうしてこういう症状がでるの?」「何をしたらいいの?」と悩む場面が少なくありません。そういった入居者の「困った行動」に対し、職員が「わかる・関われる」ようになる支援です。
療養指導では、そうした現場の“困りごと”に対して、専門家が一緒に考え、具体的な対応策を見つけていくお手伝いをします。
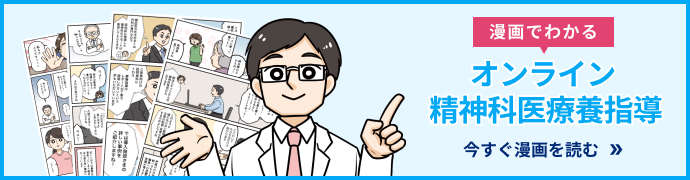
専門家を入れると、認知症ケアはどう変わるのか?
① 困りごとの背景を一緒に読み解く
例:「帰りたい」と言う理由が“寂しさ”か“昔の記憶”かを整理
→ 問題行動ではなく、「理由のある行動」として見直すことができる
- ✔︎ 利用者の行動の“意味”が見えてくることで、ケアの方向性が変わる
② 薬の使い方・減らし方についてチームで検討できる
例:落ち着かない・眠れない → 過鎮静の薬が原因の可能性も
→ 医師や看護師、薬剤師と連携し、安全な見直しのサポートができる
- ✔︎ 薬を減らせたことで、表情が豊かになった、歩けるようになった事例も
③ スタッフの“ケアの引き出し”を増やせる
例:「同じことを何度も聞く」→無視ではなく“安心できる言葉がけ”を工夫
→ 療養指導で複数の対応例を提示し、「その方に合った方法」を探せる
- ✔︎ 職員が自信を持って関われるようになり、対応力がアップする
④ 暴力や拒否がある方への“冷静な対応法”を一緒に作れる
例:暴言がある人に感情的になってしまう → 接し方のコツや関わる順番を調整
→ 状況を客観的に整理して、チームで予防策や緊急対応のルールを決める
- ✔︎ 職場全体の安心感が高まり、ケアが安定する
⑤ 家族への説明・連携のサポートもできる
例:家族が「薬を増やしてほしい」と言っている → 本人の思いとどう折り合うか
→ 専門的な立場から家族へ説明し、ご本人を中心に考える姿勢を共有
- ✔︎ 家族と施設が“同じ方向”を向いてケアができるようになる
⑥ 「話し合える文化づくり」の土台になる
例:療養指導はただのアドバイスではなく、「現場と一緒に考える時間」
→会議やカンファレンスに同席して、スタッフの意見を引き出し整理
- ✔「どうしたら良いか」を職員みんなで考える風土が育つ
▼ つまり、療養指導とは…
🔸 認知症ケアの“迷い”や“不安”を整理し、道筋を示してくれる伴走者です
🔸「すぐに正解を出す」のではなく、「一緒に考え、できるケアを増やす」支援です
🔸 医療・福祉・家族をつなぐ、“チームづくりの軸”にもなります
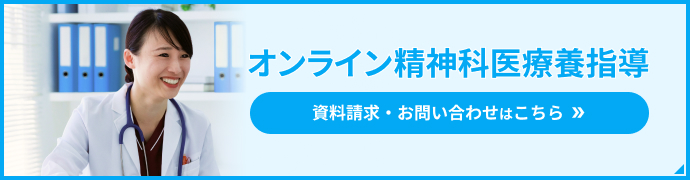
実際の施設でどんな変化があったのか?
【事例①】個人の感覚に頼っていたケアが、根拠に基づいたチームの判断に
以前は、職員の経験が頼り
療養指導導入後は、「どんな状況で?何がきっかけで?」をみんなで分析する習慣に
➤➤➤詳しい事例はこちら(ひなもり園 様)
【事例②】職員の行動が“考える・伝える”へと変わった
説明の機会が増え、職員が“自分の言葉でケアを説明”できるように
自信が生まれ、チーム間の連携も強化
➤➤➤詳しい事例はこちら(第二尾張荘 様)
【事例③】現場の雰囲気が変わった
一人で悩まない環境に
「相談してよかった」「話す場があるだけで安心」の声
➤➤➤詳しい事例はこちら(サンクレール谷津 様)
【事例④】現場を支える職員に、ケアの選択肢を与えられた
「どんな方でも受け入れたい」という志はあっても、受け入れる現場は苦労していた
ケアの選択肢が増え、自分たちで考える姿勢が身についてきた
➤➤➤詳しい事例はこちら(クイーンズビラ桶川 様)
まとめ|療養指導は、“理想のケア”を模索する第一歩
認知症ケアに、正解はありません。だからこそ“各職種のプロが一緒に考える時間”が必要なのです。療養指導は、「なんとかしたい」を「こうしてみよう」に変える小さな一歩です。
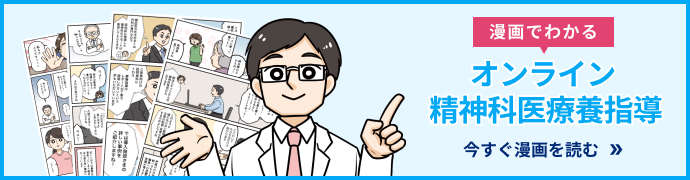
「うちでもやってみたい」と思ったら、ドクターメイト
実は精神科の中でも、認知症に精通した医師はごく少数。全国で精神科登録は約16,000名、うち認知症絡む学会登録は約2,000名で、かなりの希少人材です。偏在する認知症に精通した精神科医を探すのは簡単なことではありません。
そこでおすすめなのが、ドクターメイトの『オンライン精神科医療養指導』です。全国どこの施設でも、オンラインで認知症に精通した精神科医とつながることが可能です。
ドクターメイトの『オンライン精神科医療養指導』
『オンライン精神科医療養指導』では、軽度の段階から認知症に強い精神科医による指導を受けて、認知症ケアのアプローチ方法を見直していくことができます。
✅️ 月2回、オンラインで療養指導(30分/回)
✅️ 認知症に精通した精神科医が対応
✅️ 療養指導の記録作成をドクターメイトが作成
療養指導はこんな方におすすめ!
- 🔸 医療的な視点と現場の知恵をつなぎ、
本人にとってよりよい生活を支えるケアを目指したい - 🔸 医師に”丸投げ”ではなく、“一緒に考える場”として活用することで、
職員が自ら考えて行動できる環境をつくっていきたい
▼ ▽ ▼ 資料請求はこちらから ▼ ▽ ▼