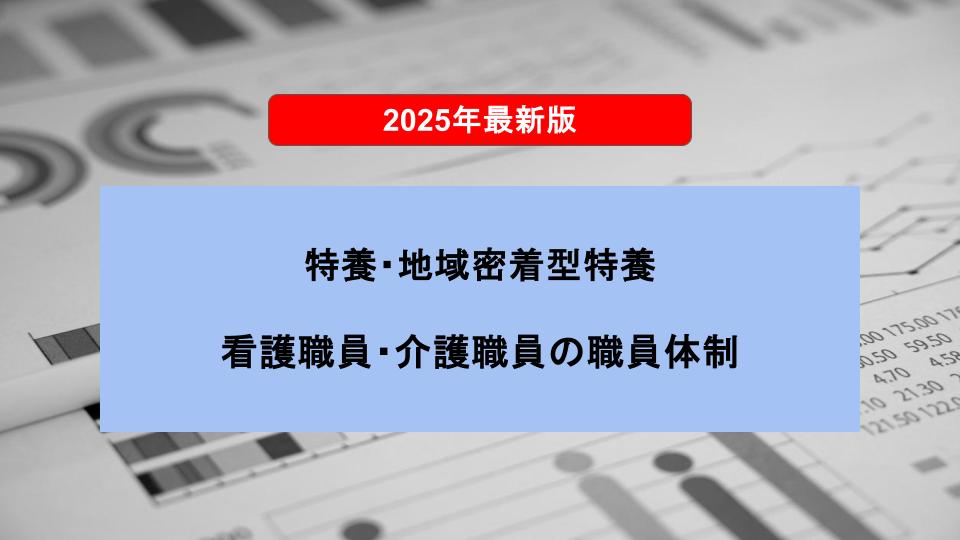厚生労働省は10月27日に開催された第127回社会保障審議会介護保険部会で、介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等における、現状と課題・検討の方向性を示しました。この「検討の方向性」は次期改定の議論において、ベースとなることから、テーマごとにまとめました。

地域の実情に応じた介護人材の確保
<現状と課題>
2040年には、65歳以上の高齢者数がピークを迎え、介護と医療の複合ニーズを抱える85歳以上人口が増加する一方で、現役世代の生産年齢人口の減少も見込まれる中、第9期介護保険事業計画に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を集計すると、2022年度の約215万人に対して、2040年度までに約57万人の新たな介護職員の確保が必要であると推計されている。
介護人材確保は重要な課題であり、処遇改善をはじめ、介護現場における職場環境改善・生産性向上の推進、介護職の魅力向上、介護現場の経営改善に向けた支援等について、国、都道府県、市町村、地域の関係者が連携し、一体的に推進していくことが重要である。
その際、高齢化・人口減少のスピードが地域によって異なる中、都道府県や市町村、地域の関係者が、地域の実情も踏まえて、人材確保、職場環境改善・生産性向上、経営改善に向けた支援に係る対策を議論し、これらの対策を講じていく必要がある。
また、その前提として、地域の状況の分析や対策を行うための基本的な考え方を国において示した上で、サービス供給面でも精緻な人材推計を地域ごとに行うなど必要なデータに基づき対策を行っていくことが必要である。
職場環境改善・生産性向上の現状・課題
<現状と課題>
「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」では、
・テクノロジーの活用や、いわゆる介護助手等への業務のタスクシフト/シェアを図ることで、業務の改善や効率化等を進めること
・それにより、職員の業務負担の軽減を図るとともに、業務の改善や効率化により生み出した時間を直接的な介護ケアの業務に充て、利用者と職員が接する時間を増やすとともに、職員の残業削減や休暇の確実な取得、教育・研修機会の付与など職員への投資を充実すること
で介護サービスの質の向上にもつなげるとともに、介護人材の定着や人材確保についてもあわせて推進することとしている。
「省力化投資促進プラン」では、2040年に向けて介護分野全体で20%の業務効率化を目標とし、セミナーや介護事業者の表彰等による優良事例の横展開や、介護テクノロジー導入補助事業の活用促進、伴走支援人材の育成など生産性向上推進施策について、2029年度までの5年間の集中的な支援を実施していくこととしている。
これまで国においては、都道府県と連携し、様々な職場環境改善・生産性向上の施策に取り組んできた。平成30年度に「介護現場革新会議」において「人材不足の時代に対応したマネジメントモデルの構築」、「ロボット・センサー、ICTの活用」、「介護業界のイメージ改善と人材確保・定着促進」を基本方針としてとりまとめ、取組の全国展開を進めるとともに、 「介護事業における生産性向上(業務改善)に資するガイドライン」を作成し、介護分野の職場環境改善・生産性向上の考え方を普及してきたほか、平成27年以降、地域医療介護総合確保基金や補正予算において介護テクノロジーやICTに係る導入支援等を行っている。また、令和6年度介護報酬改定では、施設系サービスにおいて、介護テクノロジーやいわゆる介護助手の活用等による継続的な業務改善を実施することを評価する新たな加算を設けている。
生産性の向上にあたっては、業務内容の明確化や見直しを行い、職員間の適切な役割分担(タスクシフト/シェア)を実施し、その上でテクノロジーの活用等を進めていくことが重要であり、過年度の国の実証事業においては、テクノロジーの活用及びいわゆる介護助手が間接業務を担うことによる介護職員の業務時間の削減とケアの質の向上に資する時間の増加等の結果が確認されたところである。また、国において、地域医療介護総合確保基金を活用し、いわゆる介護助手等希望者の掘り起こしや、周知活動を実施する自治体への支援をおこない、普及促進を図っている。
また、令和5年の介護保険法改正において、各都道府県が、介護サービスを提供する事業所又は施設の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努める旨の規定を新設するとともに、都道府県介護保険事業支援計画において、生産性向上に関する事項を任意記載事項に加えたところ。
それに基づき、令和5年度から各都道府県において、地域の関係者が参画した協議体である介護現場革新会議(都道府県等版「介護現場革新会議」)において戦略的に生産性向上の取組を議論して実施するとともに、介護事業者等からの相談を受け付け、適切な支援に取り組む「介護生産性向上総合相談センター」を設置しており、令和8年度までに全都道府県でのセンター設置を目標にしている。
こうした取組により、令和6年度の介護テクノロジー等の導入割合は、施設系サービスで約6割、居宅サービスで約3割となっている。このように介護テクノロジーの活用はこれまで施設系サービスにおいて先行する状況であるが、近年は居宅サービスにおいても、ケアプランデータ連携システムの活用等による業務の効率化事例もみられる。他方で、介護報酬上での生産性向上に係る取組の評価は施設系サービスのみである中、小規模事業者も含めた居宅サービス等への支援も含め、事業者の規模やサービス類型(施設、通所、訪問)等に応じた支援を行っていく必要がある。
令和5年の介護保険法改正によって各都道府県における取組は進展しているものの、介護生産性向上総合相談センターでの支援内容や各都道府県のテクノロジー導入補助金の執行状況にはばらつきがある状況である。補助金については、都道府県ごとの予算状況の公表を通じて「見える化」を図っているところだが、実施状況の地域差解消に向けて、さらに取組を進めていく必要がある。さらに、介護生産性向上総合相談センターに寄せられる相談の多くが補助金の取得に関する内容に留まっているため、補助金を含めた導入段階の支援のみならず、介護テクノロジー定着のための伴走支援、小規模事業者を含めた居宅サービスに対する相談支援等を通じ、関係者と連携し、介護事業者のニーズに応じた体制づくりを進めていく必要がある。国において令和6年度より「デジタル中核人材養成研修」を実施し、介護事業所内でデジタル化を中核的に推進する人材の養成に取り組んでいる。伴走支援に当たってはこれらの人材に加え、ICTスキルを有する人材を確保していくことも必要である。
<検討の方向性>
2040年に向けて、介護現場における人材確保・生産性向上・職場環境改善・経営改善の取組は一層重要となり、事業者の規模やサービス類型(施設、通所、訪問)等に応じた支援を講じていく必要があることから、国や都道府県、介護事業者等が果たすべき役割を制度上も明確化し、その機能強化を図るべきではないか。
併せて職場環境改善・生産性向上・経営改善支援の取組は大きな一つのプロジェクトであることから、福祉部会等で議論されている人材確保に向けたプラットフォームの枠組みの中で考えていく必要があるのではないか。具体的には、都道府県において、現行の介護現場革新会議や「介護生産性向上総合相談センター」の仕組みを発展させていく中で、これらの取組に向けた関係者との連携の枠組みを構築することを考えていくべきではないか。
その際、国において、基本方針の策定や地域医療介護総合確保基金による支援の充実を図っていくべきではないか。
さらに、人材確保・職場環境改善・生産性向上・経営改善支援について、都道府県の介護保険事業支援計画の中での位置づけを明確化するなど、地域における介護保険事業(支援)計画の策定プロセスの中で、都道府県、市町村、地域の関係者が議論し、必要な対策を講じていくべきではないか。その際、職場環境改善・生産性向上・経営改善支援に向けて、介護現場革新会議の中で地域の目標を設定し関係者の理解を醸成するべきではないか。
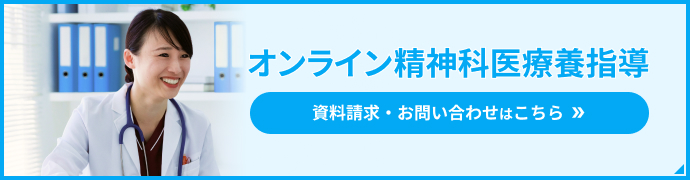
介護現場の経営改善に向けた支援、協働化等
<現状と課題>
今後、高齢化や人口減少が進み、サービス需要も大きく変化していく中、地域の実情に応じ、その変化に対応した職場環境改善・生産性向上による業務効率化、さらには事業者の経営の安定化も含めた経営改善への支援が求められる。このような中、地域の経営支援や人材確保支援に取り組む支援機関等と連携の上、生産性向上を中心に雇用管理、経営支援等もあわせて一体的に支援するような取組を進めていくことが必要である。
小規模経営をしている事業者をはじめ、介護事業者が地域に根差した上で、利用者のニーズに細やかに沿ったサービス提供を行っていくことは重要である。その上で、個々の介護事業者により経営課題が解決できない場合も、他事業者との連携・協働化、経営の多角化も含めた大規模化などにより解決が図られるケースもある。まずは、介護事業者間の協働化や連携を進めていくことが有効であり、例えば、報酬の請求や記録・書類作成事務といったバックオフィスの業務など間接業務の効率化等を進めていく必要がある。
<検討の方向性>
都道府県における経営改善に向けた支援(協働化や事業者連携等に向けた支援を含む)については、地域の実情に応じた経営課題を調査していくとともに、モデル的に実証した上で支援に向けた枠組みを段階的に構築していくべきではないか。
職場環境改善に向けたハラスメント対応の取り組み
<現状と課題>
職場環境改善に向けては、ハラスメント対応の取組を講じることも重要。介護分野では、これまでも、男女雇用機会均等法等における事業者の責務を踏まえつつ、運営基準等に係る省令において、ハラスメント対策(セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント)を義務付ける等の取組を行っている。さらに、本年6月に成立した改正労働施策総合推進法では、カスタマーハラスメントの防止のため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付けることとされており、こうした動向を踏まえた取組を行う必要がある。
ただし、認知症がある場合等には、BPSDである可能性を前提にしたケアが必要。例えば、認知症の「もの盗られ妄想」はハラスメントではなく、認知症の症状としてケアが必要であることに留意が必要。その一方で、認知症等の病気または障害に起因する暴言・暴力であっても、職員の安全に配慮することは必要であり、ハラスメント対策とは別に、施設・事業所等において、関係機関と連携して組織的に対応することが必要。
<検討の方向性>
改正労働施策総合推進法の内容等を踏まえ、全ての介護事業者に対して、運営基準等に係る省令において、現行のセクシュアルハラスメント・パワーハラスメントへの対応に加え、カスタマーハラスメントへの対応についても義務付けを行うとともに、対応マニュアルの見直しや自治体や介護事業所への周知を徹底するなど、所要の措置を講ずることが考えられるがどうか。
開発企業への支援と科学的介護の推進
<現状と課題>
介護現場の生産性向上を推進するにあたっては、ICTや技術など民間活力も活用したサービス基盤を整備していくことが重要である。そのため令和7年度にCARISO(CARe Innovation Support Office)を立ち上げ、6月にはスタートアップ支援を専門的に行う窓口を設置し、介護テクノロジー開発企業への支援を実施しており、今後さらに取組を充実させていく必要がある。
テクノロジー等を導入し、ケアの質を高めていくにあたっては、科学的根拠に基づく科学的介護を併せて推進し、そのデータを蓄積・活用していく必要がある。科学的介護情報システム(LIFE)について、令和3年度にLIFE関連加算を導入したところであるが、加算の対象サービスの事業所による届出は、施設サービス約70%、通所・居宅サービス40%にとどまっており、介護現場でのケアの質向上に向けて科学的根拠に基づく科学的介護を更に推進していく必要がある。
<検討の方向性>
科学的介護情報システム(LIFE)の更なる活用を通じて、質の高い介護を推進するため、国には科学的介護を推進していく役割があることを明確化することが考えられるのではないか。
タスクシェア/シフトについては、事業者へのアンケート調査等を通じて介護助手等の実態を分析・把握するとともに、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減の効果について引き続き検証していくべきではないか。また、引き続き介護助手等の普及を推進していくべきではないか。
今後更に介護テクノロジーを計画的に普及させていく必要があり、導入支援は引き続き重要であることから、国・都道府県においては、事業所の負担に配慮しながら、テクノロジー等の更なる活用を支援していくべきではないか。また、居宅サービス等も含め、個別のニーズに対応できるように、介護生産性向上総合相談センターにおいて伴走支援等の機能強化を図っていく必要があるのではないか。併せて、職場環境改善・生産性向上に取り組む介護事業者について、テクノロジー等の実証を十分に行った上で、介護給付費分科会において議論し、適切に報酬上も評価していくべきではないか。
厚生労働省 第127回社会保障審議会介護保険部会