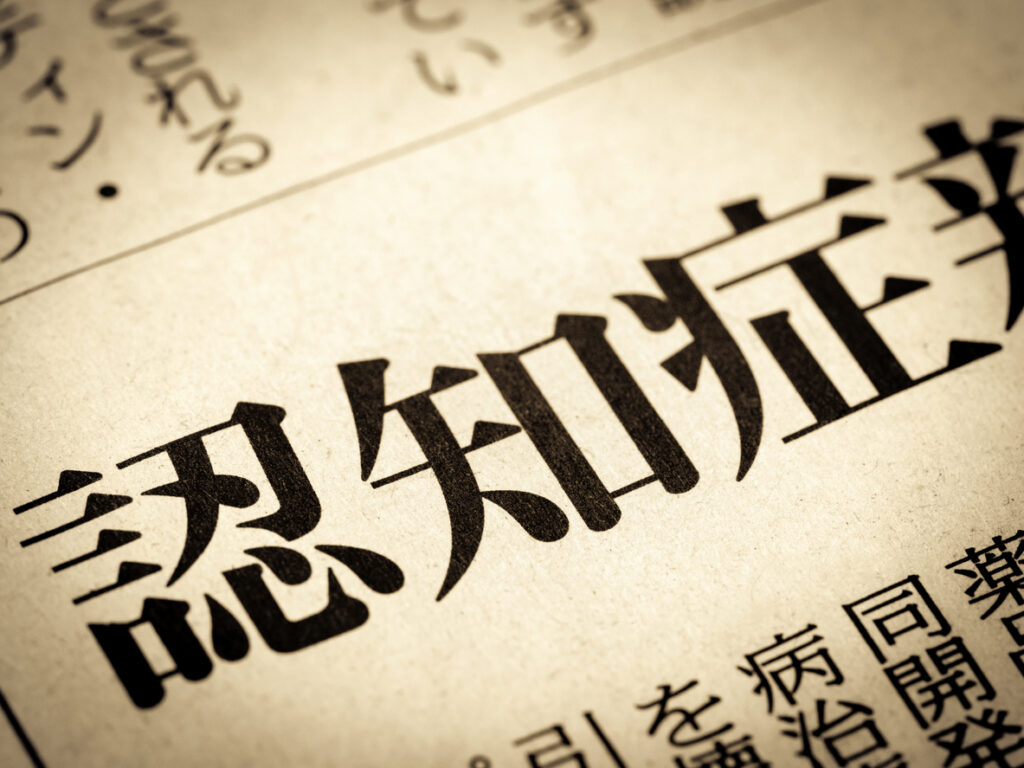2025年の春闘は労働組合の賃上げ要求に対し、満額近い回答を示す企業が続出しています。このことは昨今の物価高騰と企業側の人手不足が相まって、企業側が事実上譲歩している結果とも言えます。労働組合による賃上げ闘争の究極形は労働者によるストライキであり、かつては春闘の時期に一部企業などで行われるストライキがニュースとなりましたが、最近はそのようなことはほとんどなくなっています。近年は労働組合と使用者が協力して企業の利潤を上げ、労働者の取り分を増やそうとする「労資協調型」の労働組合が増えたことに加え、労働組合の組織率が低下していることなどがその理由とされています。
そのような中で、病院・診療所、介護・福祉施設などの労働組合が結集した日本で唯一の医療・介護の産業別労働組合(産別)である日本医療労働組合連合会(通称・医労連)が3月13日に「医療・介護を守る!3.13全国統一ストライキ」を実施しました。この背景には2024年春闘の全産業平均賃上げ率は5.1%だったの対し、厚生労働省の調査による医療・福祉分野の2024年賃金上げ率が半分以下の2.5%に過ぎず、物価高騰や過重な労働環境などが影響した離職が絶えないことなどが挙げられています。同ストライキの決議をあげた医労連加盟事業所数 は3月12日18時の時点で全国で1000カ所以上にものぼります。もっとも医労連側では、実施するストライキの中身については短時間限定や一部職員限定などにより患者や利用者の安全に影響が出ないような形で行うとしています。
今回、こうしたストライキが初経験という介護事業所もあるかと思います。また今回は避けられたものの、将来ストライキを経験する事業所もあるでしょう。そこで今回はストライキに際して雇用者側がやってはいけないことを改めて解説します。
まず、知っておかねばならないのは、労働者がストライキを行う権利は、日本国憲法第28条で定める労働基本権の団体行動の1つとして認められ、具体的には労働組合法と労働関係調整法によって規定されています。言うまでもなく日本国憲法は各種法令の頂点に位置するわけですから、ストライキとはそれだけ強力に法で守られた労働者の権利なのです。ストライキが労務不提供の範囲ならば、原則的に刑事責任も民事責任も問えず、使用者(雇用者)はストライキによって発生した損害について損害賠償請求も行えません。
まず、大原則として労働組合法第7条により、使用者は以下の行為が禁じられています。
・労働者が労働組合の組合員であること、組合活動を行ったことを理由の解雇その他の不利益な取扱い
・労働組合からの団体交渉の申し入れに対し、正当な理由なく拒否
・労働組合の結成や運営に対する支配または介入
・労働組合への資金提供
最後の資金提供については、?と思った人もいるかもしれません。これは使用者側、すなわち法人側が労働組合の活動に関わる資金を提供すれば、組合側が法人側に忖度をしかねない、要は運営の独立性が失われる危険性があるためです。労働組合に加入したことがある人ならばわかるはずですが、加入した場合は組合費を徴収されます。これが組合の活動資金となり、ストライキ実施期間中の参加者の賃金補填にもあてられます。
また、一番目の「その他の不利益な取扱い」は具体例を挙げると、ストライキ参加者に対する以下のような行為が相当します。
・福利厚生の削減 ・昇進機会の剥奪 ・教育訓練機会の剥奪 ・休暇取得の制限
・意図した労働環境の改悪 ・労働安全衛生の軽視 ・労働時間の不当な延長 ・休憩時間の削減
一方、ストライキが実施された場合、使用者側は日常の事業継続に支障をきたすことは容易に想像がつきます。これに対して非組合員の従業員や労働組合に端から加入権のない管理職を動員して事業を継続すること自体は法的に問題ありません。
さらに一般論として、ストライキ期間中に人手不足を補うために通称・スキャップと呼ばれる臨時の代替労働者を雇い入れして事業継続することも可能です。ただし、スキャップに関しては、成熟した労働組合を持つ法人の場合、予め使用者と労働組合との間で労働条件などを取り決めた「労働協約」内で禁止条項を設けていることも少なくありません。この場合は代替労働者を臨時に雇用することは認められません。なぜスキャップ禁止規定を労働協約を締結している事例が少なくないかですが、これが認められると憲法で保障されている労働者の団体行動権の1つであるストライキを無意味にしてしまうこと、さらに労使間対立が激化して解決が遠のく懸念があるからです。ちなみにスキャップ禁止規定を有するにもかかわらず、使用者がこれを破ると、ストライキ参加者から損害賠償請求される可能性も浮上します。
また、ストライキ開始前から職場にいた派遣労働者の契約更新をストライキ期間中に行うことは認められていますが、派遣先の要望に応じて派遣元がストライキ中にスキャップとして新規人材を派遣することは労働者派遣法で禁じられています。さらに公共職業安定所(ハローワーク)がストライキ中の職場に求職者を紹介することも職業安定法で禁止されています。
使用者のストライキ対抗の最終手段としては、職場を閉鎖するロックアウトもあります。ストライキ参加中の労働者の就労機会を一時的あるいは恒久的に奪い、最終的に労働者側にストライキ中止を期待する策です。医療や介護・福祉領域では、サービス提供の中断により生命や身体への不可逆的影響を被りかねない患者・利用者がいるため、使用者側が容易には採用できない手法です。しかし、すでに経営状態が悪化した小規模な介護事業所が、ストライキを起こされたことを契機に廃業をしてしまうなどの極端な事例が考えられないわけではありません。ただ、このロックアウトは使用者側に相当程度の正当性がないと法的には認められないのが現実です。
このように概観するとわかることですが、憲法と関連法令では、かなり強力に労働者の権利を擁護しています。その意味で実際にストライキを起こされた場合でも、使用者は労働組合との粘り強い交渉で事態を収拾し、安易な強硬策は避けなければならないことはお分かりいただけると思います。