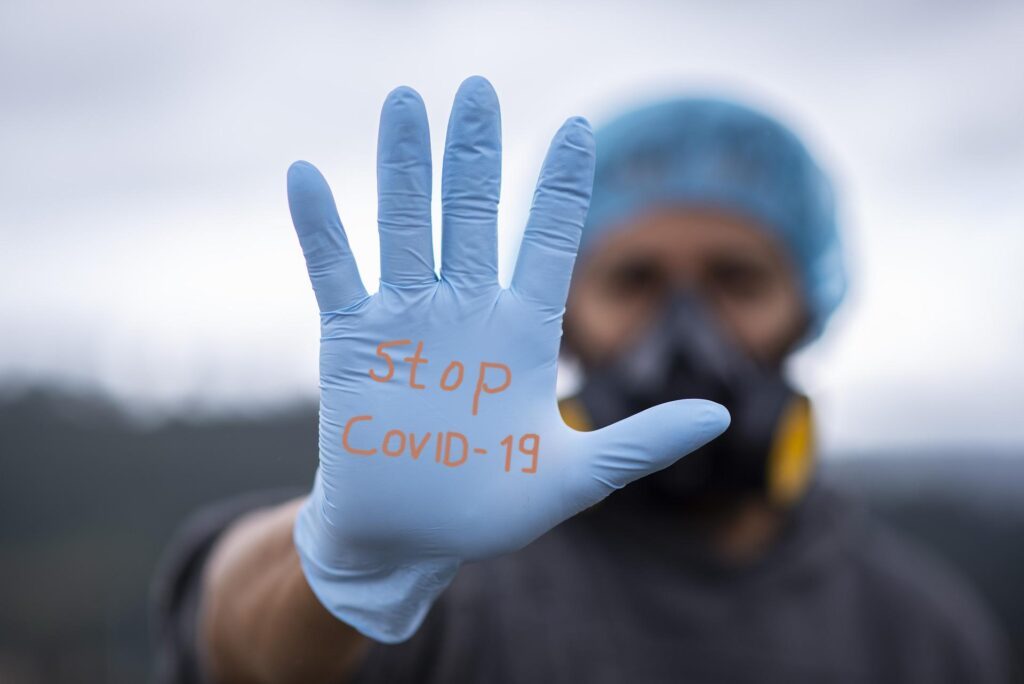現在使われている認知症の治療薬を解説する4回シリーズの3回目。
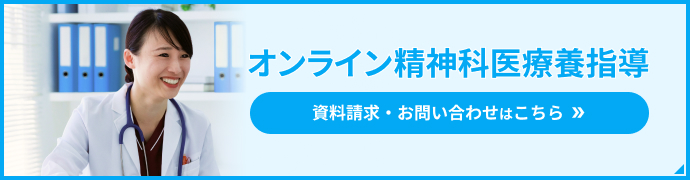
患者や家族のニーズは高いにもかかわらず、日本国内では認知症の新薬が2011年以降、10年以上にわたって登場しませんでした。
この長き“沈黙”を打ち破ったのが2023年12月に発売されたレカネマブ(商品名:レケンビ)と翌2024年11月に発売されたドナネマブ(商品名:ケサンラ)です。ともに抗アミロイドβ抗体と呼ばれる薬で、薬の効き方としてはほぼ同じです。適応症は軽度アルツハイマー型認知症とその前段階の軽度認知障害(MCI)です。
アルツハイマー型認知症では、発症の20~30年前からアミロイドβと呼ばれる異常なたんぱく質が脳内に蓄積し、その結果として脳の神経細胞が死滅し、認知機能の低下を招きます。
抗アミロイドβ抗体は、このアミロイドβにくっつくように人工的に設計された抗体を成分とした注射薬です。こうした人工的に製造した抗体を使用する医薬品は抗体医薬品と呼ばれます。
この薬は注射薬で静脈注射すると、注射液に含まれた抗体が脳内に蓄積したアミロイドβに到達して結合します。この状態になると、アミロイドβに結合した抗体を目印にその周囲に免疫細胞が集まり、アミロイドβを分解・除去します。いま脳内にあるアミロイドβを取り除くことで神経細胞の死滅がそれ以上進まないようにする原理です。
ちなみにレカネマブとドナネマブは「薬の効き方としてはほぼ同じ」と書きましたが、厳密に言うと1つだけ作用に違いがあります。これを説明するために、体内でのアミロイドβの動態を知らなければなりません。
アミロイドβが体内に最初にできた時はモノマーと呼ばれる一本の糸のような繊維状です。このモノマー同士が次第に血中で塊を作っていきます。塊の進み具合で、モノマー→オリゴマー→プロトフィブリル→フィブリル→アミロイドプラークと変化していきます。変化が進めば進むほど、アミロイドβの塊は大きくなり、かつ固くなります。そして最終段階のアミロイドプラークが脳内に沈着し、神経細胞を死滅させます。ちなみにモノマーは無害ですが、オリゴマー以降の塊は神経細胞に対する毒性があることがわかっています。
そしてレカネマブはこの塊りの中でも主にプロトフィブリルに結合し、アミロイドプラークにも結合します。これに対し、今回承認されたケサンラはアミロイドプラークのみに結合します。
この違いは投与開始後の画像診断でも確認できます。両薬剤とも効果があれば、画像上でアミロイドプラークが減少していることがわかりますが、ドナネマブの投与を受けた人の一部では投与開始から半年ほどでアミロイドプラークがほとんど確認できない水準になることが報告されています。
これをより平たく説明すると、アミロイドプラークのみを標的にしているドナネマブではより迅速にアミロイドプラークを除去するのに対し、プロトフィブリルの除去がメインで一部アミロイドプラークも除去するレカネマブはゆっくりアミロイドプラークを除去することになります。
これは「ドナネマブのほうが効果は高い」ことを意味するわけではありません。レカネマブはアミロイドプラークの手前のプロトフィブリルを主に除去し、その結果新たなアミロイドプラークが増えるのを抑えつつ、すでに蓄積されたアミロイドプラークも徐々に減らしていくということです。
一方、こうした抗アミロイドβ抗体の原理に沿うと、アミロイドβの蓄積で神経細胞の死滅がすすんでしまった患者に対して、この薬はあまり意味がないことになります。前述したようにこれらの薬の承認適応が、アルツハイマー型認知症でも早期の軽度アルツハイマー型認知症とその前段階の(MCI)であるのはそのためです。
もっとも軽度アルツハイマー型認知症やMCIというだけでなく、陽電子放出断層撮影(PET)と呼ばれる画像診断(アミロイドPET)、あるいは脳脊髄液検査(CSF検査)でアミロイドβの脳内蓄積が確認された患者のみに投与対象が限定されています。投与中に中等度以上へ進行が確認された場合は投与中止となります。
実際の使用に際しては、レカネマブは患者の体重1kg当たり10mgを2週間に1回、1時間かけて点滴で静脈注射をします。ドナネマブは初回700mgを最低30分以上かけて点滴で静脈注射し、これを4週間おきに3回繰り返します。その後は1回1400mgに増量し、4週間に1回、同じように30分以上かけて点滴で静脈注射します。
投与開始後は6か月に1回の頻度で、認知症の重症度を評価する臨床的認知症評価尺度(CDR)、認知機能障害程度を調べる「ミニメンタルステート検査」、患者や家族・介護者からの症状の聴取などを医師が行って有効性があるか否かを評価します。ここで効いていないと判定された場合、投与は中止されます。
また、前述のようにドナネマブではアミロイドプラークが画像診断上で除去されたと確認される場合があるため、投与開始から12か月後にアミロイドPETを撮影し、除去されたと判断された場合は投与完了となります。
なお、レカネマブもドナネマブも原則として投与期間は18か月と定められています。これは承認された際の臨床試験では18か月間しか投与実績がないためですが、医師が有効性と安全性を評価して必要と認められた場合はその後も投与継続が可能です。
一方、副作用については、比較的多いものがインフュージョン・リアクションと呼ばれる、注射に伴って起きる頭痛、悪寒、発熱、吐き気、嘔吐などの症状です。そして抗アミロイドβ抗体に特異的かつ時に重大になるのが「アミロイド関連画像異常(ARIA)」という副作用です。
アミロイドβは脳内で神経細胞のほかに血管壁にも貯まるため、血管の一部が脆弱になっています。このためレカネマブやドナネマブを投与すると、血管壁に貯まったアミロイドβにも抗体が結合して分解・除去する際、血管から血液の液体成分あるいは血液そのものが滲み出て、それがMRI(磁気共鳴画像)で確認されるのがARIAです。
ARIAは血管壁からにじみ出た血液の液体成分で脳組織がむくむ「アミロイド関連画像異常-浮腫/浸出(ARIA-E)」、血管から出血する「アミロイド関連画像異常-微小出血/脳表ヘモジデリン沈着(ARIA-H)」の2種類があります。
ちなみに臨床試験の設定の違いなどはあるものの、数字上のARIA-EとARIA-Hの発現率は、ドナネマブでレカネマブの約2倍になっています。これは前述の効き方の違い、ドナネマブはより大きく硬いアミロイドプラークのみを標的にしているため、血管壁に密着したアミロイドプラークがはぎとられる際に血管を損傷しやすいためと考えられています。
このように出血の可能性があることから、一般的に「血液をサラサラにする薬」と表現される抗凝固薬、抗血小板薬、血栓溶解薬などを使用している人では、より出血が起こりやすため、抗アミロイドβ抗体を使う際はより注意が必要とされています。
実際の使用ではARIAを早期発見できるよう、レカネマブの場合は投与開始 2 か月後、3か月後、6か月後、ドナネマブでは投与開始1か月後(2回目投与前)、2か月後(3回目投与前)、3か月後(増量前=通常 4回目投与前)、6か月後(7回目投与前)にMRI検査を行います。またそれ以降も6か月に1回、MRI 検査を実施する決まりになっています。
このように抗アミロイドβ抗体は、有効性、安全性に十分注意しながらの投与が求められるため、投与施設は認知症に関して十分な診療経験がある医師の常時複数在籍や高性能なMRI保有など縛りがあり、どこでも投与が受けられるわけではありません。都道府県の県レベルで見ると、県内に投与開始可能な施設が10施設未満のところがほとんどです。