
認知症では何よりも診断が重要であることは論を待ちませんが、実はこの診断が思ったより難しいのが実際です。というのも、認知症の場合、たとえば測定した血圧値で診断ができる高血圧のように明確な数値では診断できないからです。
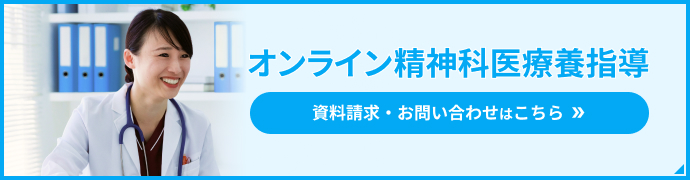
認知症診断の基本的な流れ
認知症診断の基本的な流れの1例を挙げると、
(1)問診・病歴聴取
(2)身体診察(全身の健康状態の確認)
(3)認知機能検査(記憶力や判断力などの評価)
(4)血液検査(他の病気との鑑別など)
(5)画像検査(脳の状態を詳しく評価)
(6)心理検査(うつ病などの精神的な要因を評価)の順で調べていきます。
これらの検査結果を総合的に評価して、認知症の診断が下されます。
なかでも「問診・病歴聴取」は診断のためのベースとなります。基本的な問診内容として医師はまず、患者さんや家族から以下のような情報を詳しく聞き取ります。
▽症状の経過について
- いつ頃から物忘れが目立つようになったか
- 症状はゆっくりと進行しているか、急激に悪化したか
- どのような場面で困ることが多いか
- 日常生活への影響はどの程度か
▽既往歴・家族歴
- 過去にかかった病気や手術歴
- 現在服用している薬
- 家族に認知症の人がいるか
- 生活習慣(喫煙、飲酒、運動習慣など)
▽日常生活の変化
- 料理や家事ができなくなった
- お金の管理が難しくなった
- 道に迷うことが増えた
- 性格や行動の変化
また、検査として重要になるのは「認知機能検査(記憶力や判断力などの評価)」です。冒頭で触れたように認知機能を測る明確なバイオマーカーはほとんどありません。このため認知機能の状態を点数化して評価する評価尺度が用いられます。こうした評価尺度は認知症かどうかを判定するスクリーニング検査とほぼ認知症であることを前提とした重症度判定検査があり、それぞれ複数の評価尺度が使用されています。今シリーズでは認知症の検査について主なものを解説していきます。








