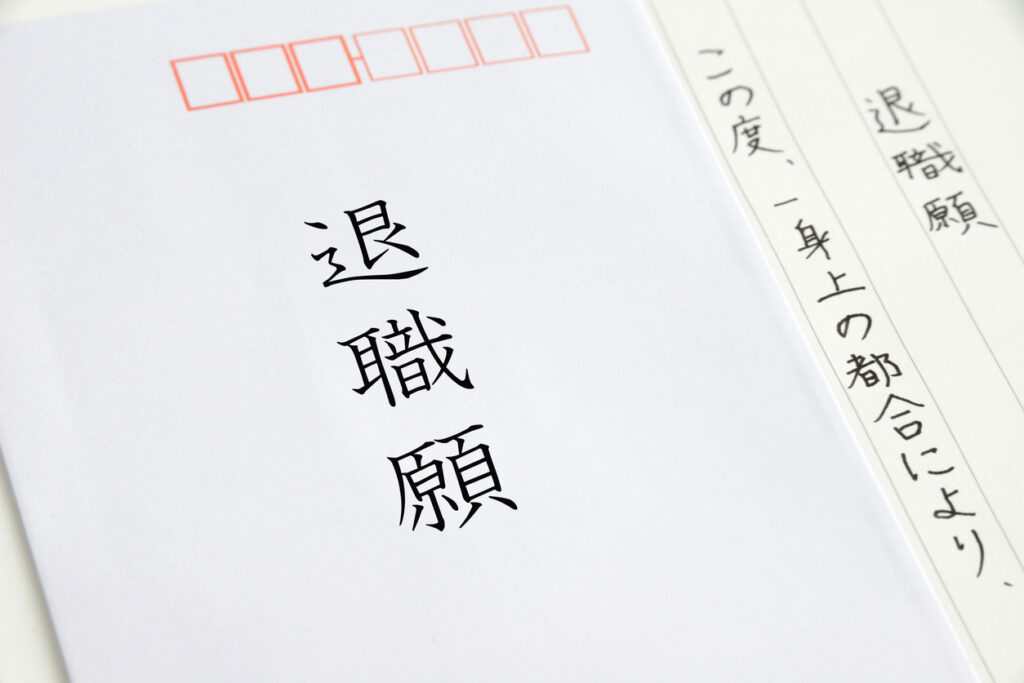認知症の診断などで用いられる検査から、血液検査、脳脊髄液検査、アミロイドβ血液検査について解説します。
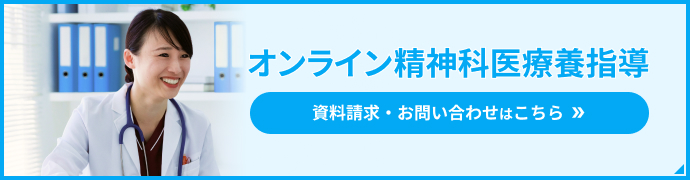
血液検査
認知症の診断では、血液検査も行われますが、その目的は主に認知機能低下の原因を特定、とりわけ他の病気が原因で認知機能が低下していないかを確認するために行われます。ただ、最近ではアルツハイマー型認知症(AD)に特異的な血液検査マーカーも近年開発されていますが、まだ幅広く使われるには至っていません。
各検査値は主に以下のような目的で行われます。
血糖値
認知症リスクになる糖尿病の有無、あるいは糖尿病による低血糖または高血糖による意識・認知障害の確認
肝機能(AST、ALT、γ-GTP)
肝性脳症、肝硬変、非アルコール性脂肪性肝炎、アルコール性肝障害による認知機能低下、薬剤性認知機能障害の確認
腎機能(クレアチニン、BUN)
薬剤性認知機能障害、尿毒症による認知機能低下の確認
電解質(ナトリウム、カルシウム)
高Ca血症や低Na血症などによる意識・認知低下の確認
甲状腺機能(TSH、FT3、FT4)
甲状腺機能低下症による認知機能低下の確認
ビタミン(B1、B12、葉酸、D)
ウェルニッケ脳症(ビタミンB1)との鑑別、B12欠乏症、葉酸欠乏症により認知機能低下や認知症リスクとなるビタミンD欠乏症の確認
感染症検査(既往歴に応じて新型コロナウイルス感染症、梅毒、HIVの抗体検査)
新型コロナウイルス感染症の後遺症、神経梅毒、HIV感染に関連する認知機能低下の確認
脳脊髄液検査
アルツハイマー型認知症では、脳脊髄液に含まれるアミロイドβ42というたんぱく質が減少し、逆に総タウタンパク、リン酸化タウタンパクと呼ばれるタンパク質が増加することが知られています。
現在、日本ではアルツハイマー型認知症が疑われる患者さんで、抗アミロイドβ抗体薬と呼ばれる注射薬の投与適応を判断する目的で、脳脊髄液内のアミロイドβ42とリン酸化タウタンパクを調べる検査が医療保険の適用となっています。
一般的にアミロイドβ42の検査値では192 pg/mL以下でアルツハイマー型認知症の可能性が高いと判断されますが、実際の臨床現場ではこのアミロイドβ42とアミロイドβ40との比(Aβ42/Aβ40)で評価します。これは脳脊髄液中のアミロイドβ42量は、脳脊髄液の採取手技や検査前の保存条件や患者の個人差などの影響を受けやすく、こうした影響を受けにくいのがアミロイドβ40だからです。一般にAβ42/Aβ40は0.06~0.07を超えるとアルツハイマー型認知症の可能性が高いと言われます。また、リン酸化タウでは参考基準値は21.5~59.0pg/mLでこれを上回るか否かで診断をします。
もっともAβ42/Aβ40もリン酸化タウもそれ単独で診断をするわけではなく、評価尺度や問診、画像診断の結果を総合して診断が下されます。
脳脊髄液検査は患者の体に負担がかかる検査であり、頭蓋内病変や意識障害などがあるケースでは実施できません。また、現時点ではどこの医療機関でも行える検査ではなく、前述の抗アミロイド抗体薬の投与が認められている医療機関で実施されています。
この検査を行う場合は、患者さんができるだけ背中を丸めてベッドに横向きに寝てもらい、腰の部分に局所麻酔をしたうえで背中側から腰椎に長い注射針を刺して脳脊髄液を採取します。なお、患者さんは採取後約1時間程度、ベッド上で安静にすることが求められます。
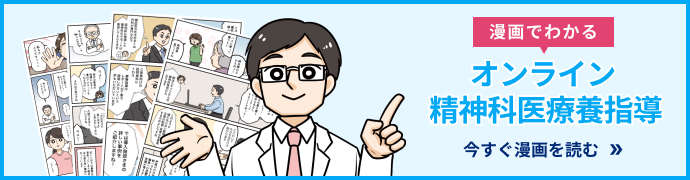
アミロイドβ血液検査
アルツハイマー型認知症の原因の一種と言われているアミロイドβの蓄積は、現状では前述の脳脊髄液検査や後述するPET検査で調べるしか方法がありませんが、両検査とも患者の負担の大きさや高い検査技術が求められるため、実施できる医療機関は限られています。このため従来から採血のみで簡便に検査できる方法が模索されてきました。
そうした中で今年5月、アメリカの食品医薬品局が日本の富士レビオ・ホールディングスの米子会社である富士レビオ・ダイアグのスティックスが承認申請していた血液中のリン酸化タウとアミロイドβ(1-42)の比率を測定する検査薬を承認しました。アルツハイマー型認知症の診断を目的に規制当局から承認を受けたアミロイドβの血液検査薬はこれが世界初です。
同社は日本国内でも年内中にこの検査薬の承認申請を行う予定です。